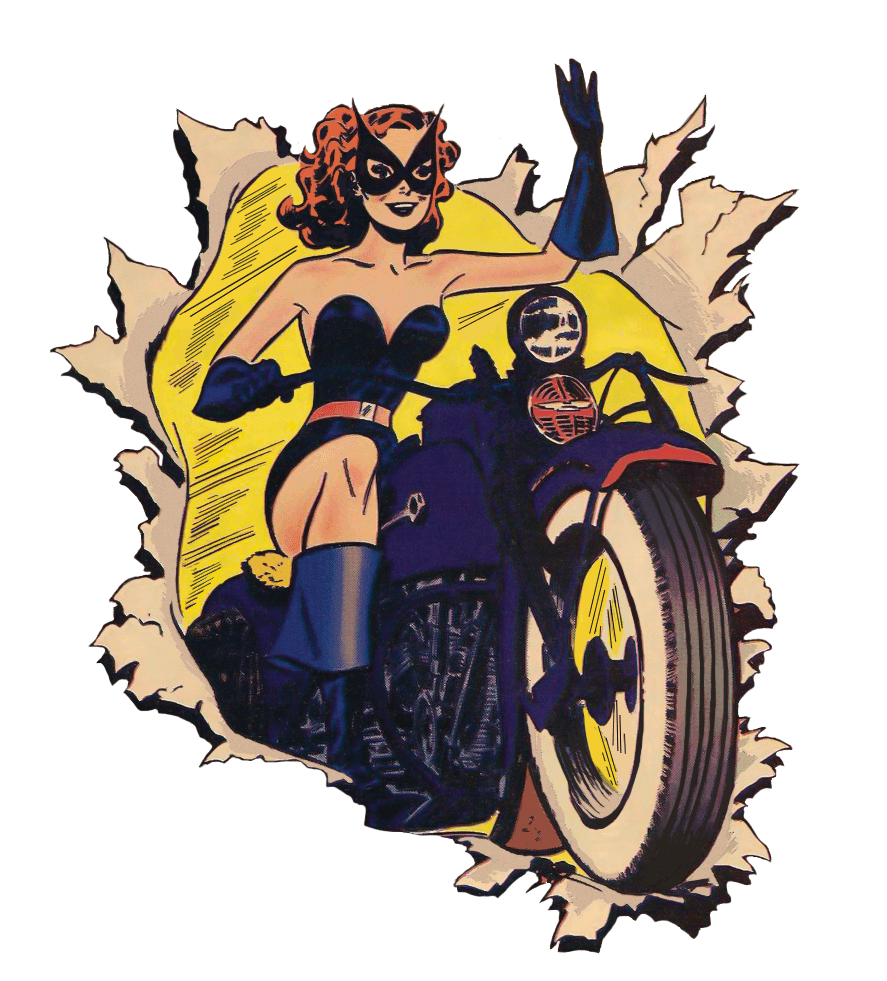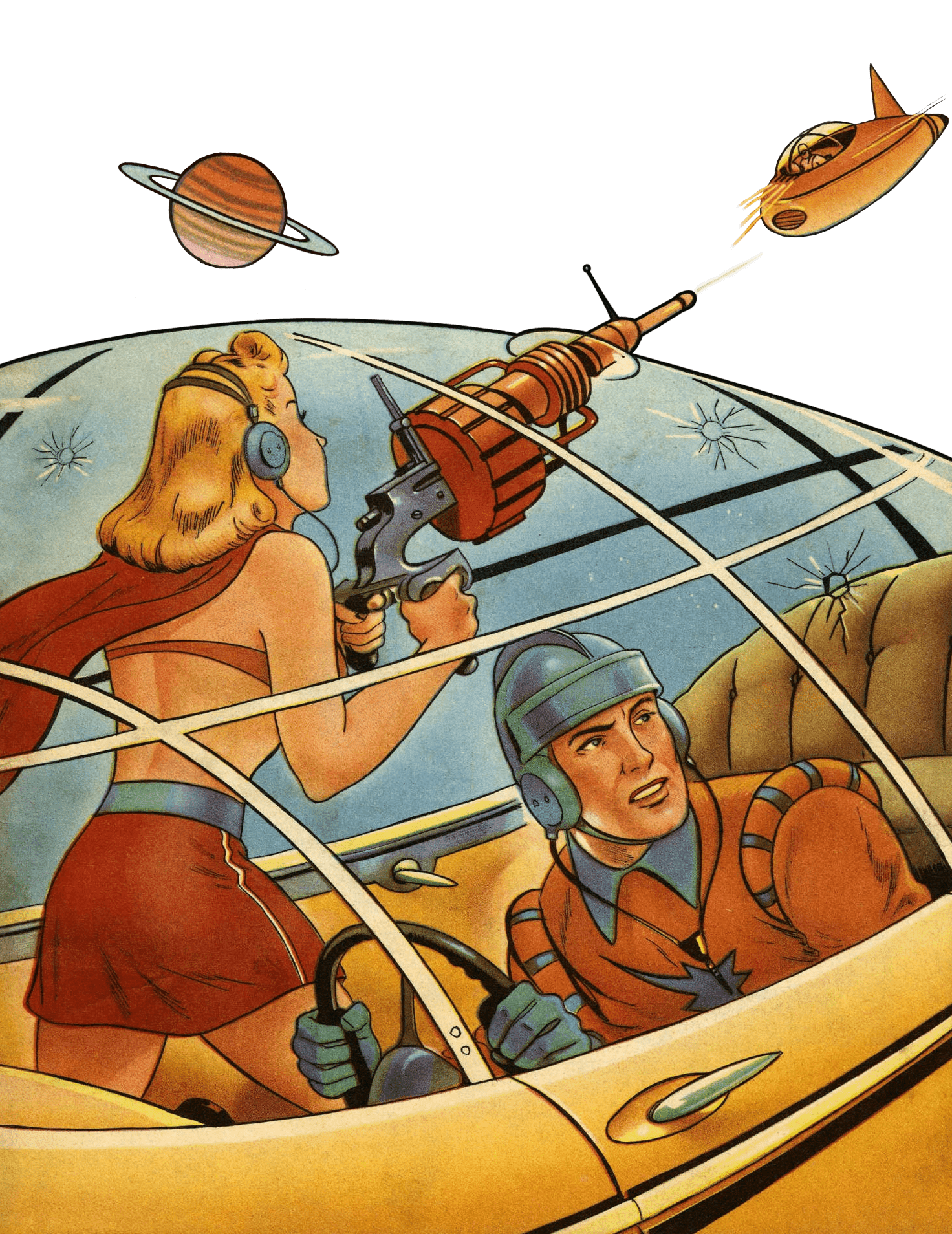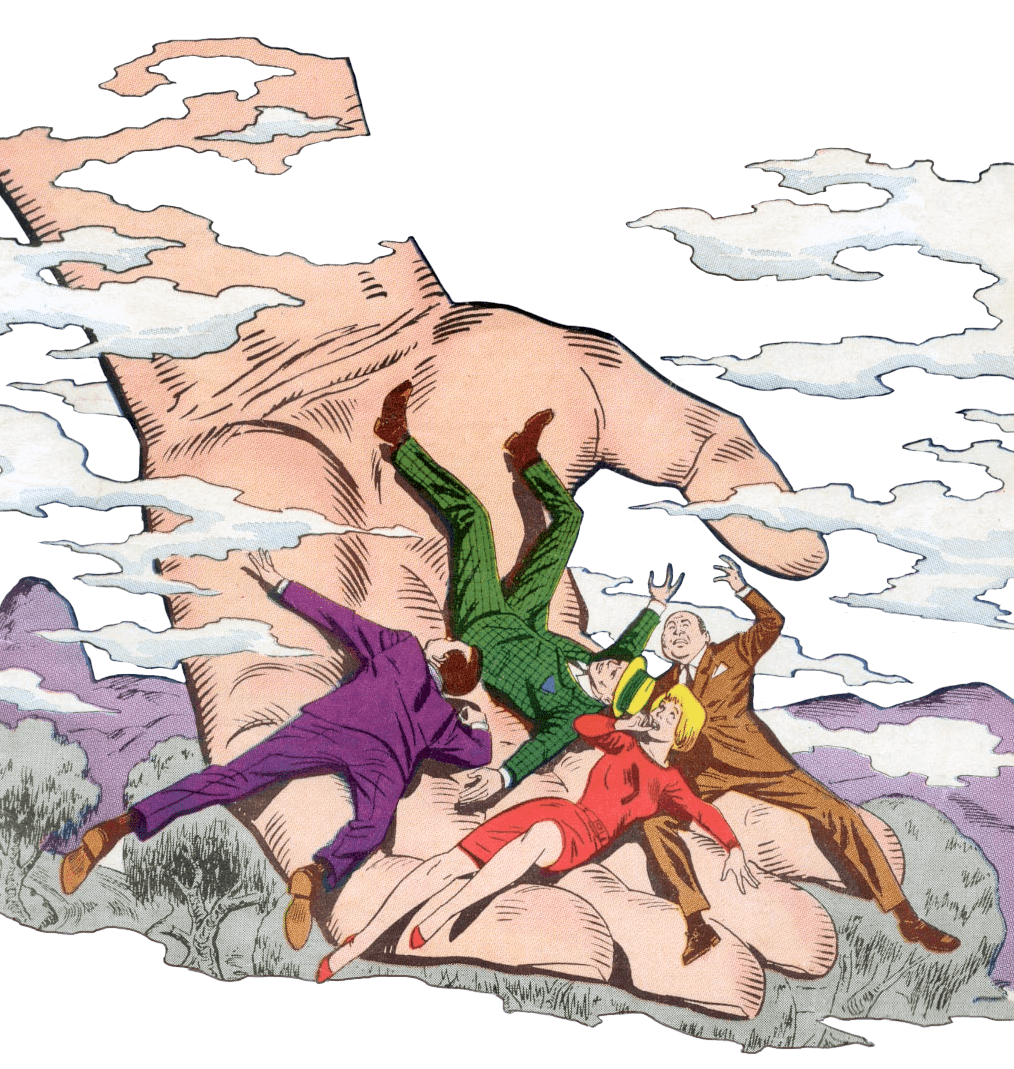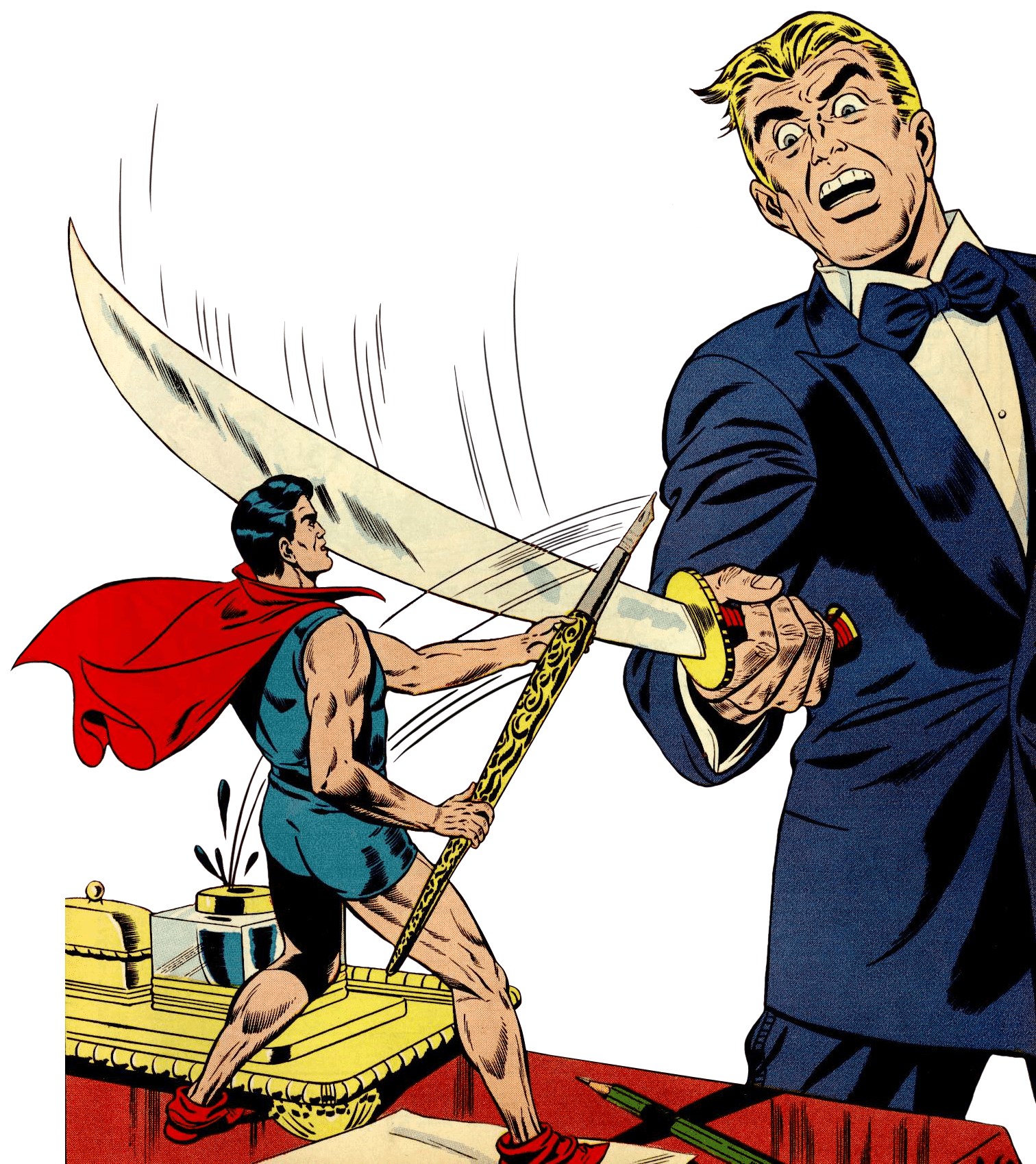試練・競争・対決
さて、ここまでで4つのアクション (優位を作る、克服、攻撃、防衛) とその4つの結果 (失敗、引き分け、成功、会心の成功) が出てきたが、これらはどのような枠組みの中で用いるのだろうか。
もし、プレイヤーが今対面している問題が比較的単純な構造である場合――たとえば荒れた川を泳いで渡る、誰かの携帯電話をハッキングするなどといった場合は、単発の行動で解決可能だ。GMの設定した難易度に対して”克服”アクションを行い、ロール結果を判断すればいい。
しかし、冒険の中には、もっと複雑な状況も存在する。そういった場合は、以下のような枠組みを用いて解決していく。
試練
試練とは、”優位を作る”や”克服”のアクションを連続して行ない、とても複雑な状況を解決するやりかただ。それぞれの克服アクションにより課題1つや状況の一部を解決し、個々の結果を総合して、どのように問題が解決されたかを見出すのである。
試練の設定時に、その局面に含まれるタスクや中間目標にどのようなものがあるかを考えよう。そのそれぞれを、別個の克服ロールとして扱っていく。
状況によって、1人のキャラクターが複数のロールを行う必要のある場合もあれば、複数のキャラクターがロールに参加できる場合もありうる。なお、GMはその試練にどのようなステップが待ち受けているのかを、先に明かす必要はない。また、GMは試練の展開に合わせて各ステップの内容を調整し、常に緊迫感を保つようにしよう。
たとえば海で嵐に巻き込まれた船乗りのPCたちが、天候にさからって突き進むことを選んだとしよう。その結果には、いくつもの要素が絡んでくるため、GMはこれを試練として扱うことを告げた。
この場合の試練を解決する手順としては、
1. 壊れた索具を修理する
2. パニックになった乗客たちをなだめる
3. 船の針路を正しい方角に保つ
などといったタスクが考えられる。
(訳注: 試練の結果どうなったかは、各アクションの結果を総合して決めていく。たとえば嵐の例では、修理に失敗した場合、船が沈んでしまうかもしれない。沈没する船から脱出する際に、乗客がパニックを起こしていた場合は、救命ボートに乗り遅れる人が出てくるという展開となるかもしれない。逆に修理には成功したが、進路を保てなかった場合は、漂流してしまい、無人島に流れ着くかもしれない。そして索具が壊れていたならば、無人島で修理する材料を探すという展開になるのかもしれない。)
競争
冒険の中には、複数のキャラクターが直接傷つけ合おうとしているわけではないが、同じ目標をめぐって競い合うような状況がある。こういった状況を競争と言う。たとえばカーチェイスや、大勢の前での討論、アーチェリーのトーナメントなどだ。
競争では、応酬と呼ばれるステップを繰り返す。各応酬では、競争者たちそれぞれが”克服”アクションを1回行い、競争の中のそのステップをどの程度上手にこなせたのかを判定する。お互いのロール結果を比べよう。
一番高い値を出した者が、その応酬に勝つ。応酬に1回勝ったことをメモし、自分のキャラクターがどう優位に立つのかを説明しよう。会心の成功をした場合は、応酬に2回勝ったものとして数える。
ロールが引き分けの場合、どのキャラクターも勝ちを得ず、その代わりに何か予期しなかった展開が起き、競争にひねりが加わる。これには状況によっていくつかのケースが考えられる。たとえば、何かしら地形や環境が変化したり、競争の枠組そのものが変化したり、不確定要素が想像以上となって、その影響が参加者全体に及んだりするのである。
(以下は訳者による例の紹介)
・地形や環境に何らかの変化が起きる。たとえば車に乗って逃亡中の犯人をバイクで追っている時に、雨が降りはじめて路面が滑りやすくなってしまう、といった場合だ。
・競争の前提や条件が変わる。たとえば海賊を目指す少年が酒場で出会った航海士に対し、お互いの持つ宝の地図の断片を賭けてダンスバトルをしようと挑んだ際に、踊りながら近くにいたゴリラのような巨体の船乗りにぶつかってしまい、ギロッと睨まれてどうしようか迷っていたところ、「おう、面白そうなことをしているじゃねえか。俺も混ぜろや!」と言われ、三つ巴のダンスバトルになってしまう、などといった場合だ。
・参加者全員に影響を与えるような、予期していなかった要素が加わる。犯人を追う例で言えば、突如として地震が発生したり、多重交通事故に両方が巻き込まれて、逃亡犯も自分もまずは無事を確保しなければならなくなるなど、まったく予想が付かないできごとにより全員がしっちゃかめっちゃかになるような場合だ。
GMはその新たな要素を表す状況アスペクトを考えて、ゲームに導入する。
応酬に先に3回勝利した者が、競争の勝者となる。
対決
対決は、キャラクターたちが互いに危害を加えようとするような場面に用いる。剣術の勝負、魔術師の決闘、レーザーブラスターでの銃撃戦など、物理的な被害を与えあう場合もあれば、罵倒合戦、手厳しい尋問、魔法による精神攻撃など、精神的な被害の場合もありうる。
状況の設定
まずは状況を明確にしよう。どのような環境で、どのようなことが起きているのだろうか。対決の相手は誰で、それぞれの居場所はどこなのか。GMはそういったことを表す”状況アスペクト”を、付箋や情報カードなどにいくつか書き、テーブルに置く (訳注:”揺れる吊橋”、”立ち並ぶ本棚”、”強風”、”壁に定間隔の松明”などといったものである)。プレイヤーからも、そういった状況アスペクトをいくつかGMに提案していい。
また、GMはゾーンをいくつか設定する。ゾーンとはその場所にある大まかなエリアのことで、キャラクターたちの位置を把握するために使う。必要ならば、手早く地図を描こう。ゾーンを区切る際には、シーンの内容と以下のガイドラインに基づくこと。
各キャラクターは、基本的に自分と同じゾーンのキャラクターに対してのみ、働きかけることができる。ただし、飛び道具や呪文を使えるなど、遠距離からでも行動を仕掛けることができる理由があれば、付近の別のゾーンにいるキャラクターに対しても行動を起こすことができる。
隣のゾーンへの移動ならば、アクションを消費せずに行うことができる。ただし、移動を妨害しようとしている者がいたり、途中に障害物がある場合は、1つのアクションを使用する必要がある。また、2つ以上のゾーンを移動する場合も、アクションを使用する。場合によっては、ゾーンを図示する簡単な地図を描くことも便利だ。
30秒でわかる対決
- シーンの状況を設定する。
- ターン順序を決定する。
- 最初の応酬を開始する。
- 自分のターン時にアクションを行う。
- 他のキャラクターのターンでは、防衛や、必要に応じて相手のアクションに反応する。
- 全員のターンが終了したら、新たな応酬を開始するか、対決を終了する。
たとえば、住宅の中にいるキャラクターたちを強盗たちが襲ってきたとする。GMは居間、台所、縁側、庭という並びでゾーンを設定した。同じゾーンのキャラクター同士はお互いを殴ることができる。居間にいるなら、隣のゾーンである台所にいる人に物を投げつけたり、アクションを消費せずに移動したりできる (戸口が塞がれていなければ)。一方で居間から縁側や庭に移動するには、 (訳注:2つ以上のゾーンを移動しているので) アクションを消費する必要がある。一方で居間から縁側を通って庭に移動するには、アクションを消費する必要がある。
ターン順序の決定
対決の中であなたのキャラクターのターンがどの順序で巡ってくるかは、あなたのキャラクターのアプローチに基づいて決まる。身体的な対決の場合は、反応速度を表す”すばやさ”でターンを得る順序が決まる。対決に参加するキャラクターたちのすばやさを比べ、最も高い者から順番にアクションを取っていく。一方で精神的な対決の場合は、”注意深さ”を比べ合う。小さな変化に気づく者ほど先を制することができるということだ。なお、複数のキャラクターのアプローチ値が同じ場合は、何らかの理にかなった基準を考え、そのキャラクターのアクションの順序を決定しよう。この際、最終的な判断はGMが下す。
GMにとって一番簡単なのは、あなたにとって行動順が最もちょうどよくなるNPCを選び、そのターン順序をGMの行動するターンとして、他のNPCも全員、そのターンに行動させるというやり方だ。しかし、NPCごとに個別に順序を決めた方がよい理由があれば、そうしてもまったく構わない。
応酬
キャラクターたちは順番にターンを得ると、前述の4つのアクションの1つを取ることができる。そのアクションを解決し、結果を判定する。そして戦えるキャラクターが一方の陣営にしか残っていない状態になると、対決は終了する。